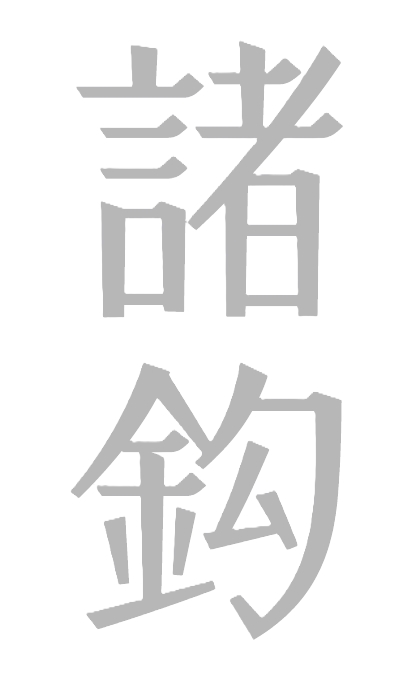

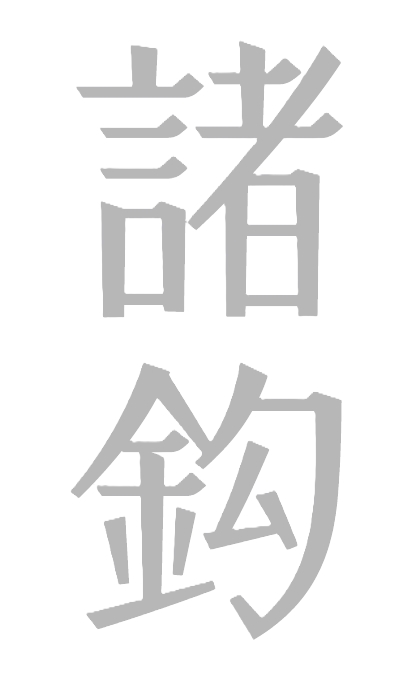


加藤峰子
デザイン、美術、現代アートやモノづくりに興味を持ち、食の分野からパン・お菓子の道を選び進む。約10年間、「イル ルオゴ ディ アイモ エ ナディア」「イル・マルケジーノ」「マンダリンオリエンタルミラノ」(ミラノ)、「オステリア・フランチェスカーナ」(モデナ)など、イタリアの名立たるミシュラン星獲得店にてペイストリーシェフを務める。「エノテカ・ピンキオーリ」(フィレンツェ)のチョコレート部門を経験。2018年より「FARO」のシェフパティシエを務める。
「FARO」では、旅するように“特別な体験として脳裏に残るようなレストラン”を目指し、日本の自然や和のハーブをリスペクトしたデザートを提案。自家製酵母など原材料からこだわりメニュー開発に取り組む。「Gault&Millau2022」にてベストパティシエ賞、「LA LISTE JAPANESE AWARDS 2024」にてトップパティシエ賞を受賞。

高田裕介
高田裕介シェフは、鹿児島県奄美大島出身の1977年生まれのオーナーシェフで、辻調理師専門学校シャトーエスコフィエ/フランスリヨンの卒業生にして、フレンチ料理の独創的な解釈と枠にとらわれない変幻自在のフリースタイルフレンチに従事。大阪の「カランドリエ」など3軒のレストランで修業した後、2007年より約2年間パリの「タイユヴァン」「ミーティング」「ホテルムーリス」など三つ星を含む数店で修行し、フランス料理の技法を学び、2009年帰国。2010年3月、大阪に自らの店「La Cime」をオープンし、2012年よりミシュランガイド関西版で一つ星、2016年より二つ星を獲得。2018年からは「アジアのベストレストラン」に名を連ね、2022年には同ランキングで6位、世界ランキングでは41位に初エントリーする快挙を達成。専門ジャンルであるフランス料理において27年の経験を持ち、常に新しい可能性を追求している。「La Cime」では、世界に認められる料理を提供しつつ、アジアのトップランクに位置し、多くの賞を受賞している。

荒井昇
1974年東京・浅草生まれ。都内レストランにて修業後、渡仏。「ル・クロ・デ・シーム(★★)」、「オーベルジュ・ラ・フニエール(★)」など数店でフランス料理の哲学を学ぶ。
2000年 帰国後、レストラン・オマージュを開業。
私は浅草で生まれ育ちました。江戸時代から長きにわたり、文化を発信し続けてきた伝統あるこの浅草で、日本ならでは、東京ならでは、僕ならではのフランス料理を発信していきたいと思っています。

夢菓房 たから(ゆめかぼうたから) (練り切り)
夢菓房たからの『素材・技・味・心』
和菓子づくりの極みは、素材選びにあり。それが「たから」の身上です。餡(あん)に使う小豆は、良質の北海道十勝産。そして味ともに誇り高き最高峰「丹波大納言」。つきあげる餅米は、近江産の「羽二重(はぶたえ)餅」。砂糖は、ふるさと讃岐の銘産「和三盆糖」を選びました。すべて、職人自らの目と舌で吟味し尽くした、選り抜きの産地限定素材。全国津々浦々の豊穣なる大地の実りを贅沢に使っています。

三友堂 (さんゆうどう) (どら焼き)
明治5年讃岐國高松藩の藩士が廃藩置県により職を失い、3人の友で和菓子屋をはじめました。これが屋号「三友堂」の由来です。
茶人・千利休遺愛の赤楽茶碗「木守」を追想し創製した代表銘菓「木守」は、昭和初期より城下町高松のみならず全国の茶道愛好家に愛され続けています。
讃岐和三盆糖を使用した和菓子を中心に、茶席用生菓子・カステラ等を取り扱っており、高松市内にて菓子原材料のひとつである獅子柚を自家栽培するなど、素材や製法を代々伝え守り続けております。

寳月堂 (ほうげつどう) (生落雁)
寳月堂は二〇一七年に創業一〇〇年を迎えました。私たちの店舗を構える丸亀は、美しいお城、穏やかな瀬戸内海、豊富な文化施設に恵まれ、多くの方々の支えの元、今日まで伝統を繋いでまいりました。ふるさと丸亀を愛し、地域に根差し、そして、丸亀・香川・四国の魅力をお菓子に想いを乗せて伝えていける会社を目指しています。
嬉しい時も、懐かしさを思い出す時も、そして日常も、お菓子が常にみなさまの話題の中心となる和やかな時を願い、今日もお菓子をお作りしております。

金谷亘 (錦玉羹、羊羹、琥珀糖)
「金谷正廣」6代目 「金谷正廣」は江戸時代末期 安政3年(1856)石川県加賀出身の[金谷庄七]が京都に出て菓子業を始めました。真盛豆を始め多種の和菓子の製造を手がけ、のちに金谷正廣と改名。以降、京都西陣の地で営業を続け現在に至ります。